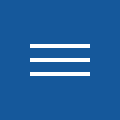インタビュー
アスリートからの伝言vol.14 フェンシング 太田雄貴さん
今できることをどれだけ精一杯やるかっていうことでしか、未来は生まれない
フェンシング界日本史上初の快挙を果たした選手が協会の会長として考えるスポーツのこれから。

公益社団法人日本フェンシング協会会長
太田 雄貴
2008年の北京オリンピックで、日本史上初となるメダル(銀メダル)を獲得した太田さんは、今、日本フェンシング協会の会長として、フェンシングの普及はもちろん、協会の運営体制や資金面の強化などに積極的に取り組み、様々な改革を起こしている。
小学3年生でフェンシングを始めた太田さん。リオオリンピックを最後に現役を引退するまでの選手生活について、そして、それを経て協会の会長となった今感じる日本のフェンシング界について話を伺った。
引退宣言、その時
―引退宣言されたのが2年前。改めて振り返ってどんな気持ちがあったのでしょうか?
太田 やめると思ってリオオリンピックに行きました。続けるっていう選択肢は無かったですね。
やりきったなというのと、最後のオリンピックで、思った成果が上げられなかった自分への失望と、すごく残念な気持ちとすがすがしい気持ちが半々に交ざるような、そんな感じですね。

―太田さんは小さい頃から勝ち続けているイメージがあって、プレッシャーみたいなものもあったのかなと思ったんですが。
太田 確かに。でも、そもそもプレッシャーがあること自体幸せな話で、人から期待されない状態で勝っても意味ないんじゃないかな~って思うんですよ。
勝って当然、勝たなきゃいけない局面で勝てるか、決めなきゃいけない局面で決められるか、人の期待を超えていけるような成果をどう上げて行くかっていうことが、自分が生きているって実感する一番の瞬間だと思うので、僕はプレッシャーをいやだと思ったことはあんまりないですね。
まあ、試合の前の日寝られないとか、逃げ出したいとか、辛いとかってあるんですけど、僕、結構忘れっぽい性格なんで、現役の頃の苦しかった記憶とかって一個も無いんですよね。
リオオリンピックの敗戦ですら良い思い出で、良い経験させてくれたなと思っているので (笑)
―負けたことさえ良い経験。どういうところにそれを感じるんですか?
太田 負ける辛さとか、人の痛みが分かったこともあります。あとは、勝ち負けにただ依存しているというよりは、フェンシングが好きかどうかを確認する場所でもあったと思っています。
フェンシングが好きなだけであれば、勝ち負けだけじゃないはずなのに、いつしか僕たちは勝つことだけを考えて、競技そのものの魅力とかを見失いがちだったりするだと思うんですよね。
そういう中で、完全に僕は勝負事の中で生きてしまっていたなという部分を、改めて感じたりとか、じゃあ、改めて「フェンシングの魅力ってなんだっけ?」っていうのを考えた2年でしたね。

フェンシングの魅力とは
―その2年で感じられたフェンシングの魅力っていうのは?

太田 フェンシングをやる人って、高潔な人が多いっていうか、インテグレイティッドな人が多いと思っています。社会にどう自分を発展させていきたいとか、フェンシングを通して感動・体験を提供するということであったりとか、子供たちに対して夢を伝えるということだったりとかもそうです。
僕たちは、今まで勝つという概念の中で楽しさを伝えようとしてたんですけど、フェンシングそのものの持つ魅力っていうのは、やっぱり努力している姿をお客さんたちに見てもらって、それが彼らの日頃の生活で「私もがんばろう!」「僕もがんばろう!」って思ってもらえるような、そういう取り組みなんだと思うんですよ。
駆け引きが魅力ですっていうのじゃ無くなりましたね。
―太田さんが日本人で初めて個人で銀メダルを獲得したり、団体でも銀メダルを獲得したりといったように、オリンピックで活躍したから、日本の中にフェンシングが広まったというのもあると思いますがいかがですか?
太田 あの時、僕は選手なので、選手にとっての最大の目標ってオリンピックの金メダルで、メダルを獲って人生を変えたいとか、メダルを獲ってフェンシングをもっとみんなに知ってもらいたいとか、正直、その程度のことしか考えて無かったと思うんですね。
現役を離れて2年、フェンシングがメダルを獲ったのに人気スポーツに変わらなかった課題は、どの辺りだったのか?ものすごく気づく2年でした。
それは、役割だと思うんですよ。選手には選手の目標があるし、協会の会長としては協会の会長としての目標があるので。
僕、本当に選手の時代の頃を振り返らないし、思い出さないんですよね。なんだろうな、今しか無いと思っていて、今できることをどれだけ精一杯やるかっていうことでしか未来は生まれないと思っているんです。過去から学ぶこと、歴史から学ぶことはあれど、自分の人生を振り返ることは、ふとした瞬間だけやこういう取材の時くらいしか振り返らないですね。でも、現役時代に仲間と闘った経験が、今の協会の運営や人を巻き込むっていう礎になっていると思います。
フェンシングが面白くなったのは21歳

Photo by:竹見脩吾
―太田さんは小学校3年生の時、お父さんがきっかけでフェンシングを始めたそうですが、最初から楽しいと思っていたんですか?
太田 僕がフェンシングを面白いと思うようになったのは21歳ぐらいなんですよ。それまでは面白いと思っていなくて、多分、フェンシングじゃなくても何でも良くて、上手くなる感覚とか、相手に勝つとか、勝って褒められるとか、特に小学生くらいの頃は、勝ったら親が喜んでくれるっていう、承認欲求ですよね。
その承認欲求を満たして行くためにフェンシングがあったって言って嘘にならないんじゃないかな。本当に、自分のためにフェンシングをやって「超楽しいな~。」と思ったのは親から自立してからですね。
―なぜ、そんな風に思えるようになったんですか?
太田 それまで親のためにやっていたのが、自分のためにやろうっていう風に切り替わる瞬間が来たんです。その時期ちょっと過ぎた辺りの頃、僕、京都から東京に出てくるんです。
やっぱり誰かのためにやっている間はダメですね。勝っても負けても自分のせい。責任の所在を人に委ねない。絶対に自分がやるって思えた辺りから、人生の選択を自分で決めているから後悔が無いんです。
やらされていると思うと、プロはきついですよ。
スポーツってすごく素晴らしいことだと思いますけど、プロとしてやっていくためには、それ相応の時間を失うわけですからね。自分が他のことをできたかもしれない時間を、その競技に充てるっていうことが、どれだけ人生にとってリスクが高いかってことを分かった上で挑んでいますからね。本当にきれい事じゃ無いですから。しかも、報われる人はほんの一部です。
だから僕は二兎を追ったら上手くいかないと思ったので、就職しないで北京オリンピックに挑んだんです。
褒めるには余裕が必要

―子供の頃の承認欲求の話がありましたが、子供は褒めた方が伸びるんですかね?
太田 褒めた方が良いんじゃないんですか?褒めることによるデメリットないんじゃないですか?
褒めるっていうのは、親御さんも余裕がないと褒められないんですよ。良いところを見つけるって、実は結構、能力が高くないとだめなんですよね。しかも、クリティカルなタイミングに褒めるためには子供のことをよく見てないとダメなんですよね。
子供をけなすっていう行為や叱るっていうのは、自分に余裕がない表れだと思うんです。例えば、子供を勢いで叱る時って余裕が無いんですよ。寝ている時に赤ちゃんが泣くとイラっとするのは、自分が眠くて余裕がないんですよね。
ある種、褒めて伸ばすっていう人は自分に余裕がある人じゃないですかね。
うちの親父とか、めちゃめちゃ余裕がありましたもんね。そもそも自分の価値観の中にお金っていうものがないし、出世欲も名声を上げたいっていうのも一切無くて。家族を一番に考えて、5時には家に帰って来ていましたからね。残業という感覚を僕は知らなかったです。仕事は5時に終わるものだと思っていました。夕食は、必ず家族全員で食べていて、たまに誰かが塾でいないっていうのはあれど、祖父と祖母も一緒に必ず7人でご飯食べていましたね。
―それはフェンシングの強さに関係していると思いますか?
太田 どっちかっというと、人のことを好きになりますよね。みんなで何かをやるのが好きになるし、しかも親から愛されたなっていう感覚が強いから、いま、協会の会長として選手たちに、お金を出してあげられない代わりに、めちゃめちゃ時間を使っているわけですよ。
本当だったら、僕が働いて得られていただろうお金を含めたものを放棄して、フェンシング協会の会長として無給でやっています。普通はやらないだろうって思いますよ。だって、無給で週40時間も協会に業務時間を使ってますから。
僕がなんでやっているかっていうと、みんながやらないところに突っ込んでいくことに価値があると信じてやっているんですよ。普通やらないだろうっていうところは尖りやすくなるけど、新しい世界を切り開けると思っています。
ノーという人を置く

―逆張りすると、それを悪く言う人もいるんじゃないですか?
太田 僕は気にしないです。だって、その人にとって酒のつまみでしかないでしょう。ほんとに僕のことを人生においては重要とは思ってないでしょう。それは逆もしかりで、僕にとっての彼らって、そんなに重要じゃないし。
それってなんだろうな、みんなに好かれたい人は、何かを遂行する気概が無いんですよ。僕もずっとそうでした。でも、この2年で考え方が変わったんですよ。それまでは、みんなに嫌われないように、みんなに好かれるように、周りの目を見て決断していたんですけどね。
もちろん、余計な敵を作ったり、余計なけんかはしないですけど、これだって決めて賛否がある場合も僕が決めたんで支持してくださいって言います。ちゃんとしたロジックを持って、ガバナンスは効かせないといけないので、きちんとしたプロセスを経て実行まで行きますけど。
あと、否定されても気にしないです。それは、違った意見があるっていうことを前提に話すので。同調は何も生み出さないですよ。僕の周りは、僕にノーと言う人をたくさん置いています。
―意見の違いが出た時は、どう受け止めているんですか?
太田 その瞬間は、「マジか?」って思いますけど、家に帰って寝て考えると冷静になるんで、「あれも一理あるな」って。
熱くなっている時は決断しないです。熱くなって決断する時はろくなことが無いので、だいたい一旦、一晩寝かせて「これで行きます。」って。
―非常に若くして会長になっていますが、その若さに協会側も託されたのかなとも思いますがいかがでしょう?
太田 そうかもしれないですけど、スタート時は僕の会長というのは満場一致じゃないんですよ。当然、賛否ありました。だから僕は今までに無い会長像で、自分の全てを使って発信もするし、汗もかくし、やっぱり汗をかかないとダメだなと思ったので、そこは徹底的にやりました。
汗をかいた経験が、必ず僕に生きてくる。最初の3年は、汗をかこうと思いました。特に最初の1年でしたね。汗いっぱいかいたの。でも今の2年目も変わんないです。
―お話を伺っていると、いろんな逆境を力に変えている感じがしました。私たち、日常生活をしていると逆境を力に変えられなかったり、くじけたりしますが、太田さんはどうやって力に変えているんですか?
太田 僕もくじけていますよ。心折れそうですよ。折れてますよ。折れたところから始まってますから僕の場合。だけど、絶対に諦めないですね。
僕の周りはすごい人が多いんです。すっごい経営者ばっかりで、彼らは絶対諦めないし、僕の何十倍も努力しているし、僕が最近すごいってスポーツ界で言われますけど、足元にも及ばないですよ。僕なんて5流ですよ。
だけど、5流でも賞賛されるっていうのは、スポーツ界の課題ですよね。もっともっとすごい人はいっぱいいます。彼らに少しでも近づけるように、彼らとは違う努力の仕方とか、そういう闘い方ですね。

子供たちへ向けて

Photo by:竹見脩吾
―協会の会長になって、子供たちに向けてというのはどういうことを考えていますか?
太田 家庭環境にかかわらず、教育と運動する機会っていうのは与えられるべきだと思っているんです。ただ、みんなに等しく機会を与えられる競技と、そうじゃない競技があると思うんですね。ボール一つでできる競技もあれば、道具が必要でなかなか敷居が高いものもあります。
そういったときに、必ずしも運動っていうのは、自分が体を動かすっていうだけじゃなくて、例えば、人を応援する題材のためにスポーツがあっても良いと考えています。
その一つに、僕たちが行っている学校訪問プロジェクトでは小学校を訪問してフェンシングを生で見てもらうというのをやっているんですけど、600人~700人の子供たちが、声が枯れるまで戦う選手を応援するんですね。観ることで心が豊かになるっていうのもスポーツの役割だと思うんですよ。
だから、フェンシングを始める始めないにかかわらず、フェンシングを観戦する楽しさを提供し続けたり、誰もが始めやすいようなフェンシングっていうのを開発して行くっていうことで、子供たちに機会を提供して行きたいですね。
―子供たちへのメッセージをお願いします。

太田 なかなか好きなこととか、やるべきものって見つからないと思うんですよね。だけど、「自分が興味持っているのってなんだっけ?」っていうのを考えるんじゃなくて、すぐ手と足を動かしに行く。ちょっと良いなって思ったら、向いている向いていないを考えずに、とりあえずやってみる。とりあえずやってみた中に自分の向き不向きを分別できるものが混ざっていると思うので、とりあえず、ひたすら打席に入る。ひたすら打席に入ってバットを振り続けるような機会を持って欲しいですね。
で、親御さんは、子供にどれだけ打席に立つ機会を作ってあげられるかっていうのを、やり続ける。それでしか変わらないと思うので、正解が一つじゃない世の中で、正解っていっぱいあるよねっていうことを親子で学ぶような、そういう新しい教育だったり、スポーツっていうのが出てくると面白いなと思っています。

太田 雄貴(おおた ゆうき)
1985年生まれ。京都府出身。
元フェンシング日本代表選手
現在、日本フェンシング協会会長、世界フェンシング連盟理事
2008年 北京オリンピック男子フルーレ個人で日本フェンシング史上初の銀メダルを獲得
2012年 ロンドンオリンピック男子フルーレ団体戦で日本史上初の団体銀メダル獲得
2016年 リオデジャネイロオリンピック出場後、現役引退を表明。